好きな小説について語るだけ
投稿日:2025/3/31
春休みに実家に帰省した際に、小学生の頃よく通っていた市民図書館を訪れた。古本特有の匂いとひんやりとした空気、適度な静けさの中に響く紙を捲る音が心地よく、一日中図書館に籠って小説を読み漁った。手に取った本の殆どは10年以上前に読んだもので、細かい内容は忘れてしまっていたものの、ページをめくるたびに当時の情景が思い出されて、まるで小さなタイムカプセルを開けているようで、ノスタルジックな気持ちになっていた。
中学は部活、高校はプログラミング、大学は競プロと物理で忙しく、あの頃に比べれば読書量はめっきり減ってしまったけれど、小説はずっと好きだ。図書館に行ってから数日が経つが、未だに懐古の念に駆られている。そこで、このブログサイトの記念すべき一本目の記事として、これまでの自分の読書遍歴を振り返りつつ、好きな小説について語ってみようと思う。
1. 児童文学
今までの人生で読んだ本の数は恐らく数千冊程度だと思うが、その殆どは小学生時代に読んだもので、さらに言えばその大半を児童文学が占めているだろう。スポーツ系の習い事はいくつかやっていたが、それ以外の自由な時間はほぼすべて読書に費やしていた。
振り返ってみると、当時の読書の楽しみ方は今のそれとは異なっていたように思う。小学生の頃は酸いも甘いも大して経験していないので、キャラやストーリーに共感しながら読むというよりは、無限大の想像力で描写の余白を補っていた。そのおかげで、どんなに現実離れした内容でも熱く深く物語に没入できた。一方で今は、記憶の中から近い感情や体験を引っ張り出してきて、それを作中の表現と重ねながら読んでいる節がある。もちろん、それはそれでより生々しい追体験を得られるので悪くはない。ただ、記憶がある種の制約にもなっていて、昔のように自由に想像力を膨らませて幅広い世界観を楽しむことは難しくなってしまったのが、少し寂しくもある。
思い出に強く残っている本をいくつか挙げてみる。
マジック・ツリーハウス
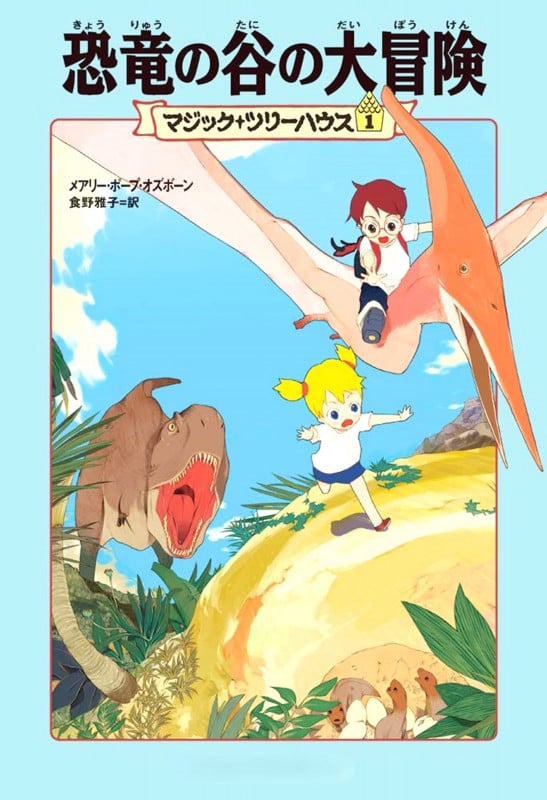
小学校に上がって初めて借りた絵本以外の本がこれだった。今振り返ると、全学年で大人気だったこのシリーズの1巻が、たまたま誰にも借りられずに本棚に置かれていたのはとても幸運だった。ツリーハウスという舞台装置、本を通じて色んな時代・場所を冒険できるという設定、年の近い魅力的なキャラクターたち、何より絵本と比べると圧倒的なボリュームがあり長く楽しめるという点が、当時の自分にとってはとても魅力的だった。まるで自分が冒険しているかのような感覚を味わえたし、自分が本格的に読書にハマるきっかけになった本の一つだと思う。
低学年の頃は、このシリーズを皮切りに、「サーティーナイン・クルーズ」、「パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々」、「ドラゴン・スレイヤー・アカデミー」など、海外の児童文学のシリーズものにドはまりしていた。
ぼくらの七日間戦争
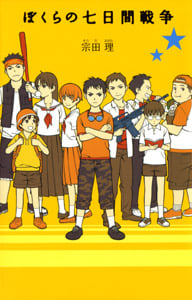
言わずと知れた名作。仲間とくだらないことをして笑ったり、真剣に悩んだり、大人たちに立ち向かったり、その姿がとても輝いて見えて夢中で読み進めた。初めて手に取ったのは小2の頃で、「学生運動」や「恋のABC」など意味を理解できない単語も多かったが、それも含めて「何か凄いことをしている」、「中学生のエネルギーってすげー!」とワクワクしながら読んでいた。複数の出版社からでているが、個人的には小学校の図書館に置かれていたポプラ社の版が一番思い入れがある。表紙の絵も好きだし、ハードカバーなのも特別感があって良い。もうしばらく新刊はでていないので難しいのかもしれないけど、キリよく「ラストサマー」まで出版してくれないかなぁ…。
一年ほど前のニュースですが、今でも強く印象に残っています。「ぼくらシリーズ」は間違いなく自分の人生に影響を与えた作品の一つでした。いつまでも、大好きです。
ふたり

これは小学6年生のときに読んだ本で、確かその年の読書感想文の課題図書だったと思う。
講談社児童文学新人賞入選作家最新作。本が大好きな小学生二人が図書館で覆面作家の謎を解きながら育む淡い恋と友情の物語。
放課後に転校生の小野佳純さんの机に女子数人が何かをしているのを見てしまったは村井准一は、どうしてもそのことが気になって、友達と別れた後にこっそり六年三組の教室へ戻って小野さんの机を覗きこんでいた。ちょうどその時、教室の扉がいきなり開いたかと思うと、そこに立っていたのはなんと小野さん本人だった……。
クラスでこっそりといじめにあっている転校生の小野佳純とそのいじめを見つけてしまった村井准一は、二人とも同じミステリー作家、月森和が大好きだったことを知って仲良くなる。その月森和が別名で他にも本を書いていることと、実はその秘密が既刊本の中にあるらしいという情報を得た二人は、図書館へ通って謎説きに夢中になるのだった──本が大好きな二人の淡い恋と友情の物語。
「紀伊国屋書店 ふたり 出版社内容情報」より引用
あらすじを見ても分かる通り「高学年向けの王道の児童図書」といった感じ。読後感がとても良く、心が温まる作品。主人公のふたりの聡明さや純粋さ、クラス全体に漂う圧とそれに逆らえない弱さ、淡い恋心と決心、行動力、登場する大人たちの温かさ。多くの理想的な要素の上で成り立っている物語で、でもところどころにリアリティもあって、いろんなバランスが絶妙だった。この良さを的確に表現することばを持っていないのがもどかしい。
大学生になった今でも、定期的に読んでいる。少し話がズレるが、いつか誰かのツイートで見た「文字が滑って読めない」という状態には共感できるものがある。そういうときに読み返したくなるのがこの本だ。他にも、「ブルーとオレンジ」、「さよならミイラ男」、「幽霊魚」など、福田隆浩さんの作品には好きなものが多い。その中で特に「ふたり」は、今でも自分の中で特別な位置を占めている作品だと思う。
2. ライトノベル
小学校高学年から中高にかけて、ライトノベルを読む割合が増えた。といっても、中高の読書量は小学生の頃の100分の1も無かったので、この節もほとんど小学生の頃の読書遍歴になる。
ところで、Wikipediaによると、ライトノベルの明確な定義はないらしい。
業界内でも明確な基準は確立されておらず、はっきりとした必要条件や十分条件がない。このため「ライトノベルの定義」については様々な説がある。
とはいえ「まぁ大体こんなもん」というゆるいお気持ちはあるようで、検索するといくつか解説サイトがヒットする。そのうち、小説家(ライトノベル作家)の杉井光さんの書いた「『ライトノベルの定義』に対する最終回答」というNote記事では、以下のように結論づけられている。
ライトノベルとは、
『十代後半あたりの青春期に抱く憧れを、読者の心を惹きつけるための原動力として恥じることなく用いた小説』のことである。
記事全体を通して「なるほど~」と思う部分が多く、個人的にはとても納得感があった。
自分が「ライトノベルかな」と思う作品のなかで、特に好きだったものをいくつか挙げる。
フォーチュン・クエスト
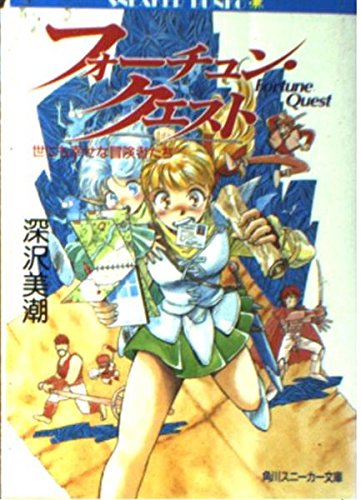
多分、僕が人生で初めて読んだライトノベルだと思う。元々「IQ探偵ムー」という作品が好きで、そこから著者の深沢美潮さんの他の作品を探して、市民図書館で見つけたのがこの本だった。
いまでないとき。
ここでない場所。
この物語は、ひとつのパラレルワールドを舞台にしている。
そのファンタジーゾーンでは、アドベンチャラーたちが、それぞれに生き、さまざまな冒険談を生み出している。
(中略)
わたしはこれから、そのひとつのパーティーの話をしたいと思っている。
彼らの目的は……まだ、ない。
フォーチュン・クエスト各巻冒頭のモノローグより引用
このモノローグがとても好きで、読んだ瞬間に一気に心を掴まれたのを覚えている。
このシリーズを一言で表すなら、「ポンコツパーティーの冒険譚」が一番近いだろうか。主人公はマッパーのくせに方向音痴だし、リーダーの戦士はお人好しでいつも貧乏くじを引いてばかり、口の悪い盗賊はギャンブル好きでいつもトラブルを持ってくる。メモを見ながらでないと呪文を唱えられない幼いエルフと、寡黙で優しく小動物と会話のできる巨人、知力は高いが変わり者の農夫もいて、なんて愉快なパーティーなんだろうと思った。決して優秀ではないけれど、ときに笑い、ときに涙しながら、仲間たちと共に小さな、たまに大きな冒険を続けていく。少しずつ成長していく彼らの姿がとても愛おしく、同時に勇気をもらった。
「フォーチュン・クエスト」は、「新フォーチュン・クエスト」、「新フォーチュン・クエストⅡ」と名前を変えながら続いていたが、2020/07/10に発売された「新フォーチュン・クエストII(11) ここはまだ旅の途中<下>」をもって完結した。中学に入ってからも図書館に追加されるたびに借りて読んでいたが、実は最終巻まではまだ追えていない。「新フォーチュン・クエスト」の途中までは買っていて、いつか全巻紙で揃えたいと思ってはいるものの、一人暮らしの身としてはお金と場所(本棚)を工面するのが難しく、なかなか手を出せないでいる。この記事を書いてたらめっちゃ読みたくなってきた…。
キノの旅

「フォーチュン・クエスト」と同じ頃に出会った作品。ざっくり纏めると、旅人キノとモトラド(注・二輪車。空を飛ばないものだけを指す)のエルメスが旅をする物語だ。内容的にはほぼ独立している短編が複数収録されていて、風刺的な話、クスっと笑える話、感動的な話、ガンアクションなど、ジャンルは様々である。基本的には淡々とした語り口で話が進むが、戦闘描写などはかなり生々しく、当時の自分とっては衝撃的だった。
「キノの旅」の魅力は沢山あるのだけど、一番インパクトが大きかったのは「あとがき」だ。「キノの旅」は最初図書館で借りて読んでいたのだけど、ハマりにハマったので、小学4年生のときにクリスマスプレゼントとして、そのとき出ていた分を全巻買ってもらった。もちろん、うっきうきで次の日から何周も読み返していたのだけど、外れかかったカバーを整えようとして”それ”に気づいたときは本当にびっくりした。図書館の本はカバーがテープで丁寧に固定されていたので、図書館で満足していたら一生気づかなかったかもしれない。後々、そういう装飾は漫画のコミックス単行本などではよくあるものと知ったが、小学生の自分はその概念を知らなかったので、まさかそんな仕掛けがあるとは思ってもみなかった。もう一度言うが、あのときの衝撃は本当に凄かった。
著者の時雨沢恵一さんの書く文章の空気感とギャグ(?)センスがとても好きで、「キノの旅」以外にも「学園キノ」、「アリソン」、「リリアとトレイズ」、「メグとセロン」など、色んな作品を読んだ。
本当はもっと色々書こうと思っていたのだけど、上で挙げた2作品以外は最後に読んだのが5年か、下手したら10年近く前なので、記憶が曖昧でなかなか手が動かなかった…。
パッと出てくる範囲で、印象に残っている作品を挙げると
よく読んでいた著者さんを挙げると、
- 川原礫さん
- 成田良悟さん
- 西尾維新さん
- 松村涼哉さん
といったところだろうか。いつかまとまった時間ができたら、また読み返したいなぁ。
3. ミステリ
特に「ミステリにハマった時期」というのは無いのだけど、父親がミステリ好きで家にそこそこ本があったので、自然と手に取るようになった。といっても、僕はマニアックなミステリファンではないので、読んだり見たりした作品は有名なものばかりだと思う。
小学校の図書館で好んで借りていたのは、江戸川乱歩の「少年探偵団シリーズ」や「シャーロック・ホームズ」などの古典的な作品が多かった。特に、少年探偵団シリーズは「怪人二十面相」というカリスマ的な悪役がいて、盗みはするが暴力は振るわないというスタンスがとても好きだった。もちろん少年探偵団も「小林少年」や「チンピラ別動隊」、「七つ道具」など魅力的なキャラクターや設定があって、厨二心をくすぐられていたのを覚えている。
父親の影響で読んでいたのは、東野圭吾さん、綾辻行人さん、森博嗣さんの作品が多かった。
- 夢幻花(東野圭吾)
- 白銀ジャック(東野圭吾)
- マスカレード・ホテル(東野圭吾)
- 流星の絆(東野圭吾)
- ナミヤ雑貨店の奇蹟(東野圭吾)
- 十角館の殺人(綾辻行人)
- どんどん橋、落ちた(綾辻行人)
- Another(綾辻行人)
- すべてがFになる(森博嗣)
パッと思いついたものを書いてみたけど、どれもかなり好き。本格ミステリも好きだし、ミステリ以外の要素が強い作品も好きだ。ミステリを読むと「頭を使わなきゃ」という気持ちになるので最近はあまり手を出さなくなってしまったけど、実家に帰ったときにまた読み返してみようかな。
スプラッタやホラー系も実家にあって何冊か読んだのだけど(ex. リング、殺人鬼、黒い家)、一人暮らしを始めてからは読もうと思えなくなってしまった…面白いんだけどね…。
4. 大学生になってから
大学生に入って、読書量がまた少しずつ増えてきた(それでも小学生の頃には遠く及ばないが)。読書の楽しみ方もまた変わってきて、「ドキドキワクワク」を強く求めるのではなく、「人と人との触れ合い」、「人情の機微」、「人生観」などに興味を持つようになった。あまり愉快な話ではないけれど、大学入学以降の環境の変化や、精神状態の影響を大きく受けているのだろうと思う。
大学生になってから読んだ本の中で、特に印象に残っているものを挙げる。
ミミズクと夜の王

自らをミミズクと名乗る身も心も廃れた奴隷の少女と、魔の森を統べる夜の王の物語。切なく哀しいラブファンタジー。
「読書メーター ミミズクと夜の王 あらすじ」より引用
本当に好き。何度も読み返している。この例えが適切かは分からないけれど、「大人向けの童話」のような作品だと思っている。悪人側はとことん極悪非道で、善人側はみな清廉で芯の通った生き方をしている。舞台設定がハイファンタジーなこともあって、現実からはかけ離れたとても綺麗で美しい物語という印象を受けた。
同じ舞台設定で「毒吐姫と星の石」という作品も出ていて、こちらも好き。やはりおとぎ話のような柔らかい雰囲気があり、「ミミズクと夜の王」に登場したキャラクターの成長した姿が描かれているのも嬉しい。
この2作品にはかなり複雑で大きい感情を抱いているのだけど、これを100%文字に起こせる自信はないし、無理に型にはめて言語化しようとすると安っぽくなってしまう気もする。ただ、自分の表現力の乏しさは日々痛感しているものの、言語化できるものだけで世界が構築されているわけではないとも思う。何が言いたいかというと、めっちゃいい作品です。めっちゃ好き。
スロウハイツの神様

若者のクリエイターたちが共同生活を送る「スロウハイツ」というアパートを舞台に、人間関係の変遷やそれぞれの成長を描いた作品。ミステリ要素もあって、読み返してみるとたくさんの伏線が張られているのが分かる。ただ、個人的にこの作品の一番の魅力は「人間模様」だと思っている。いやこれも上手く言語化できないし、出来たところで語り尽くせないのだけど、本当にキャラクターが魅力的なのだ。ストーリーも綺麗にまとまっていて温かさがある。大学生になってからは、こういう温かさを作品に求めるようになったように感じる。
著者の辻村深月さんの作品は他にも7~8作品は読んでいるが、好きな作品が多い。「ぼくのメジャースプーン」、「名前探しの放課後」、「かがみの孤城」、最近読んだものだと「傲慢と善良」もかなり好みだった。「スロウハイツの神様」は、辻村深月作品の中で現時点でのマイベスト。
大学生になって読んだ本のうち、三分の一くらいを辻村深月さんの作品が占めていた。そう考えると全然読書量増えてないな…。
最近は、森見登美彦さんの「夜行」や「四畳半神話大系」を読んで、もう少し他の作品も読んでみたいなと思っている。他に気になっているのは、町田その子さんの「コンビニ兄弟」、凪良ゆうさんの「流浪の月」、「汝、星のごとく」、2024年に本屋大賞を受賞した宮島未奈さんの「成瀬は天下を取りにいく」など。時期的に今買っても積むだけなので、院試を終えたあたりから少しずつ手を出していきたい。
5. 懐かしのタイトル
最後に、この前図書館に行ったときに見かけた懐かしい本をいくつか挙げておく。時間が無くて読み切れなかったもの、巻が抜けていて読めなかったものがたくさんあるので、また実家に帰ったときにでも借りて読みたい。
- シェーラ姫の冒険
- マリア探偵社
- 妖怪ナビ・ルナ
- シノダ!チビ竜と魔法の実
- 内科・オバケ科ホオズキ医院
- 黒魔女さんが通る
- 風の陰陽師
- チームふたり
- 獣の奏者
- 二分間の冒険
- 都会のトム&ソーヤ
- ドラゴンラージャ
- バッテリー
- 一瞬の風になれ
- キケン
6. おわりに
思ったよりも長くなってしまった…。書いているとどんどんと思い出がよみがえってきて、止まらなくなってしまった。時間はかかったけど楽しかった。ここに挙げていない作品で思い入れの深いものはいくらでもあるし、僕が思い出せないだけでひっそりと自分の人生に影響を与えた作品もたくさんあると思う。もうその全てを思い出すことはないのだろう。
今の小学生はどんな本を読むのだろうか。昔の自分のような本の虫が今の小学生にもいて、その子たちが手に取る本のなかには僕が通ってきた作品もきっとある。時間を忘れて夢中でページをめくっていたあの宝物のような時間を、今の子たちが同じように過ごしているのだとしたら、それはとても尊いことのように思う。逆に、今の子たちが影響を受ける僕が知らない作品たちを、同じような温度で楽しめないのがとても悔しい。僕はもう小学生では無くなってしまった。
まぁそんなことを言っていてもどうしようもない。小学生の頃には戻れないが、小学生の自分では楽しめなかった作品があるのも事実だ。そういう作品に一冊でも多く出会えるように、これからも本を読み続けていきたいと思う。